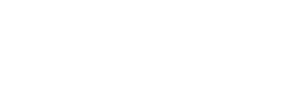うつ病で障害年金はもらえる?受給の条件・申請手続の流れ・注意点を社労士が徹底解説
目次

うつ病を患い、仕事や日常生活に大きな支障が出ている方にとって、経済的な不安は切実な問題です。そのような状況で心の支えとなり得るのが「障害年金」です。
「うつ病でも障害年金がもらえるの?」「どうすれば申請できるの?」「自分だけで手続きするのは難しそう…」
こうした疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。この記事では、障害年金申請代行を専門とする社会保険労務士が、うつ病で障害年金を受給するための条件、申請手続の流れ、そして申請における重要なポイントや注意点について、わかりやすく解説します。
現在うつ病で苦しまれている方、またそのご家族の方が、この記事を読むことで障害年金制度への理解を深め、少しでも経済的な不安を和らげる一助となれば幸いです。
うつ病で障害年金を受給するための基礎知識
まず、障害年金とはどのような制度なのか、そしてうつ病がどのように障害年金の対象となるのかについて確認しましょう。
障害年金とは?
障害年金は、病気やケガによって、法律で定められた障害の状態になった場合に支給される公的な年金です。障害年金には、初診日に加入していた年金制度によって、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。
- 障害基礎年金: 原則として、初診日に国民年金に加入していた方(自営業者、専業主婦(夫)、学生、無職の方など)や、20歳前に初診日がある方が対象です。障害等級は1級と2級があります。
- 障害厚生年金: 初診日に厚生年金に加入していた方(会社員や公務員など)が対象です。障害等級は1級から3級まであり、3級よりも軽い障害状態の場合には障害手当金(一時金)が支給されることもあります。
うつ病も障害年金の対象です
「精神疾患では障害年金はもらえないのでは?」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、うつ病をはじめとする精神疾患も、障害年金の支給対象となります。具体的には、「精神の障害用」の認定基準に基づいて、障害の程度が審査されます。
重要なのは、単に「うつ病である」という診断だけではなく、うつ病によって日常生活や就労にどれだけの支障が生じているか、その「程度」が審査の対象となる点です。
うつ病で障害年金を受給するための3つの条件
うつ病で障害年金を受給するためには、主に以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
- 初診日要件:初めて医師の診療を受けた日がいつか 「初診日」とは、うつ病の症状で初めて医師または歯科医師の診療を受けた日を指します。この初診日にどの年金制度に加入していたかによって、受給できる障害年金の種類(障害基礎年金か障害厚生年金か)が決まります。また、後述する保険料納付要件を満たしているかどうかの基準日にもなります。 初診日の証明は障害年金申請において非常に重要であり、カルテなどの客観的な資料に基づいて行う必要があります。
- 保険料納付要件:年金保険料を一定期間納めているか 初診日の前々月までの公的年金の加入期間において、以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。
- 年金保険料の納付済み期間(免除期間、猶予期間、学生納付特例期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること。
- 初診日が令和8年3月31日以前にある場合は、初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと(特例)。
- ご自身の保険料納付状況がわからない場合は、年金事務所や市区町村の年金窓口で確認することができます。
- 障害状態要件:障害の程度が認定基準に該当するか 障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日、または症状が固定した日)において、うつ病による障害の程度が、国民年金法施行令・厚生年金保険法施行令に定められた障害等級に該当する必要があります。
うつ病などの精神の障害における障害等級の目安は以下の通りです。- 1級: 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの(他人の援助がなければほとんど自分の用事を済ませられない状態)
- 2級: 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの(必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度)
- 3級 (障害厚生年金のみ): 労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- これらの等級は、医師が作成する診断書の内容や、ご自身で作成する「病歴・就労状況等申立書」などを基に総合的に審査・判定されます。
うつ病の障害年金申請における重要なポイント
うつ病で障害年金を申請する際には、他の傷病とは異なる特有の難しさや注意点があります。
- 症状の波と日常生活能力の的確な伝達: うつ病の症状は、良くなったり悪くなったりと波があることが一般的です。申請書類には、症状が良い時だけでなく、悪い時の状態や、その波によって日常生活や就労にどのような支障が出ているのかを具体的に記載することが重要です。日常生活能力の判定に関する医師の評価も重要なポイントとなります。
- 就労状況の評価: 「働いていると障害年金はもらえない」と誤解されがちですが、必ずしもそうではありません。就労している場合でも、その仕事内容、勤務時間、職場での配慮の状況、収入などを総合的に考慮し、障害の程度が判断されます。 例えば、一般雇用であっても著しい援助や配慮を受けている場合や、障害者雇用枠での就労、就労継続支援A型・B型事業所での作業なども、障害年金の審査において考慮される要素です。どのような状況で働いているのかを正確に伝えることが大切です。
- 診断書の重要性と医師との連携: 障害年金の審査において、医師が作成する「精神の障害用の診断書」は最も重要な書類の一つです。医師に日常生活や就労で困っている状況、症状の具体的なエピソードなどを正確に伝え、実態に即した診断書を作成してもらうことが不可欠です。日頃からご自身の状態を記録しておき、診察時に伝える準備をしておくと良いでしょう。
- 病歴・就労状況等申立書の適切な作成: 「病歴・就労状況等申立書」は、発病から現在までの経緯、日常生活の状況、就労状況などを本人が記載する書類です。診断書だけでは伝えきれない具体的なエピソードや困難さを、審査機関に伝えるための重要な書類となります。時系列に沿って、診断書の内容と矛盾がないように、客観的かつ具体的に記載することが求められます。ご自身で作成するのが難しい場合は、社労士などの専門家に相談することも検討しましょう。
障害年金申請の流れ(うつ病の場合)
うつ病で障害年金を申請する際の一般的な流れは以下の通りです。
- 年金事務所・市区町村役場への相談: まずは最寄りの年金事務所や市区町村の年金窓口に相談し、障害年金制度の説明を受け、必要な書類(年金請求書、診断書様式など)を入手します。この際に、初診日の確認方法や保険料納付要件についても確認しておくと良いでしょう。
- 初診日の証明書類の準備: 初診日を証明するための書類(受診状況等証明書など)を、初診の医療機関に作成依頼します。初診の医療機関と診断書を作成する医療機関が異なる場合に必要となります。
- 医師への診断書作成依頼: 障害認定日以降に、通院している医療機関の医師に「精神の障害用の診断書」の作成を依頼します。日常生活や就労における支障について、事前にメモなどにまとめて医師に伝えると、より実態に即した診断書を作成してもらいやすくなります。
- 病歴・就労状況等申立書の作成: 発病から現在までの日常生活や就労の状況、受診歴などを具体的に記載します。ご自身の言葉で、正直に、わかりやすく書くことが大切です。
- 年金請求書等の作成・提出: 年金請求書に必要事項を記入し、収集した診断書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書、その他必要書類(戸籍謄本、住民票、預金通帳の写しなど)を添えて、年金事務所または市区町村役場に提出します。
- 審査・結果通知: 提出された書類に基づいて、日本年金機構で審査が行われます。審査には通常3ヶ月~半年程度の時間がかかります。審査結果は郵送で通知されます。
社労士に障害年金申請を依頼するメリット
うつ病の障害年金申請は、ご自身でも行うことは可能ですが、手続きが複雑で、書類作成にも専門的な知識が求められるため、精神的に大きな負担となる場合があります。社会保険労務士に申請代行を依頼することで、以下のようなメリットがあります。
- 複雑な手続きの代行: 初診日の調査・確定から、必要書類の収集、年金請求書や病歴・就労状況等申立書の作成、年金事務所への提出まで、一連の手続きを代行します。
- 的確な書類作成サポート: 障害年金の認定基準や審査のポイントを熟知しているため、受給可能性を高めるための的確な書類作成をサポートします。特に「病歴・就労状況等申立書」は、ご本人の状況を審査員に効果的に伝えるための重要な書類であり、専門家によるサポートは大きな力となります。
- 年金事務所との円滑なやり取り: 年金事務所からの問い合わせや追加書類の要求などにも、専門家として適切に対応します。
- 受給可能性の向上: これまでの経験と専門知識に基づき、個々の状況に応じた最適な申請方法をアドバイスすることで、ご自身で申請するよりも受給の可能性を高めることが期待できます。
- 精神的な負担の軽減: 煩雑な手続きや書類作成のストレスから解放され、治療に専念することができます。
うつ病の障害年金に関するよくある質問
Q1. 働いていても障害年金は受給できますか?
A1. 就労しているからといって、必ずしも障害年金が受給できないわけではありません。仕事の内容、勤務時間、収入、職場での配慮の状況などを総合的にみて、障害の程度が判断されます。例えば、障害者雇用枠での就労や、一般企業でも相当な配慮を受けて就労している場合などは、受給できる可能性があります。まずは専門家にご相談ください。
Q2. 申請してから結果が出るまでどれくらいかかりますか?
A2. 一般的に、申請書類を提出してから結果が出るまでには、障害基礎年金で約3ヶ月~4ヶ月、障害厚生年金で約4ヶ月~半年程度かかると言われています。ただし、書類の不備や審査状況によっては、これ以上かかる場合もあります。
Q3. 自分で申請するのは難しいですか?
A3. ご自身で申請することも不可能ではありません。しかし、障害年金の制度は複雑で、特にうつ病などの精神疾患の場合は、症状の伝え方や書類の書き方に注意が必要です。診断書の内容や病歴・就労状況等申立書の記載内容が審査に大きく影響するため、不安な場合は専門家である社会保険労務士に相談することをおすすめします。
Q4. もし不支給になった場合、どうすれば良いですか?
A4. 障害年金の請求が不支給となった場合や、決定された等級に納得がいかない場合は、「審査請求」という不服申し立ての手続きを行うことができます。審査請求には期限がありますので、結果通知を受け取ったら速やかに専門家にご相談ください。
ご相談は静岡障害年金サポートきぼうへ
うつ病による日常生活や仕事への影響は、ご本人にしかわからないつらさがあると思います。経済的な不安が少しでも軽減されれば、治療に専念しやすくなり、症状の改善にも繋がる可能性があります。
うつ病で障害年金の受給をお考えの方は、決して諦めずに、まずは一度、障害年金専門の社会保険労務士にご相談ください。当事務所では、お一人おひとりの状況を丁寧にお伺いし、障害年金受給の可能性や申請手続きについて、親身にサポートさせていただきます。
この記事が、うつ病で苦しむ方々とそのご家族にとって、少しでもお役に立てれば幸いです。
プロフィール

- 社会保険労務士
-
ご覧いただきありがとうございます。
三島市・富士市・沼津市・熱海市・伊豆全域・御殿場中心に
静岡県全域の障害年金の請求サポートをしております。
障害年金について気になることやご質問があれば
お気軽にご相談ください。
一人でも多くの方が明るい未来へと歩み出せるよう、
全力でサポートいたします。
最新の投稿
- 7月 7, 2025コラム障害年金の遡及請求とは?過去分の受給可能性と申請ポイントを社労士が解説
- 7月 7, 2025コラム働きながら障害年金はもらえる?受給の可否を左右するポイントを社労士が解説
- 7月 7, 2025コラムがんで障害年金はもらえる?ステージ・治療中の申請ポイントを社労士が解説
- 7月 7, 2025コラム人工透析で障害年金はもらえる?等級2級の基準・申請時期を社労士が解説
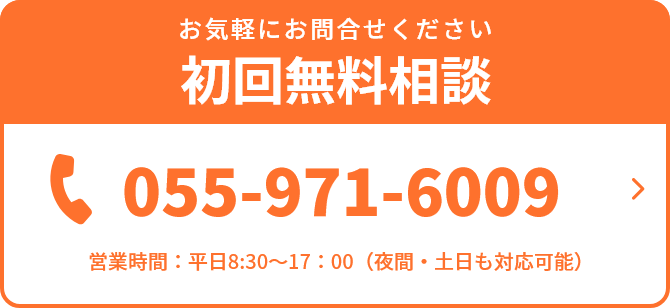
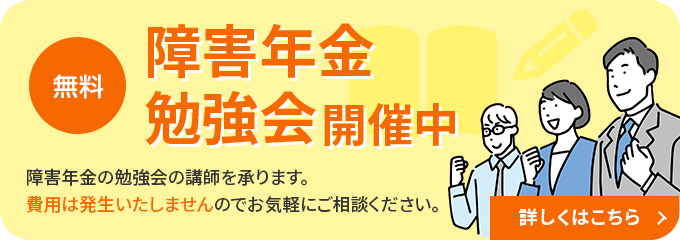

 初めての方へ
初めての方へ