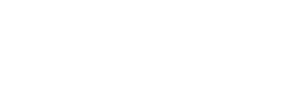統合失調症で障害年金は受給できる?条件・申請方法・注意点を社労士が解説!
目次
統合失調症は、幻覚、妄想、思考の混乱、意欲の低下といった多様な症状が現れる精神疾患であり、ご本人やご家族の生活に大きな影響を与えることがあります。「将来への経済的な不安を感じる」「治療に専念したいけれど、生活費が心配」といった悩みを抱えている方も少なくないでしょう。
そのような状況において、経済的な支えとなるのが「障害年金」です。
この記事では、障害年金申請代行を専門とする社会保険労務士が、統合失調症で障害年金を受給するための条件、申請手続の流れ、そして申請における重要なポイントや注意点について、わかりやすく解説します。
統合失調症と向き合いながら生活されている方、またそのご家族の方が、この記事を通じて障害年金制度への理解を深め、少しでも経済的・精神的な負担を軽減するための一助となれば幸いです。
統合失調症で障害年金を受給するための基礎知識
まず、障害年金制度の概要と、統合失調症がどのように障害年金の対象となるのかについてご説明します。
障害年金とは?
障害年金は、病気やケガによって、法律で定められた障害の状態になった場合に支給される公的な年金です。初診日に加入していた年金制度に応じて、主に以下の2種類があります。
- 障害基礎年金: 初診日に国民年金に加入していた方(自営業者、専業主婦(夫)、学生、無職の方など)、または20歳前に初診日がある方が対象です。障害等級は1級と2級です。
- 障害厚生年金: 初診日に厚生年金に加入していた方(会社員や公務員など)が対象です。障害等級は1級から3級まであり、3級よりも軽い障害状態の場合には障害手当金(一時金)が支給されることもあります。
統合失調症も障害年金の対象です
統合失調症は、精神の障害として障害年金の支給対象となります。「精神の障害用」の認定基準に基づいて、症状の重さだけでなく、それによって日常生活や社会生活にどれほどの制約が生じているかが総合的に審査されます。
統合失調症の主な症状には、以下のようなものがあります。
- 陽性症状: 幻覚(幻聴など)、妄想(被害妄想、誇大妄想など)、思考の混乱など。
- 陰性症状: 感情の平板化(喜怒哀楽の表現が乏しくなる)、意欲の低下、引きこもり、思考の貧困など。
- 認知機能障害: 注意力・集中力の低下、記憶力の低下、計画・実行能力の低下など。
これらの症状が、どの程度日常生活や就労能力に影響を与えているかが、障害等級を判断する上で重要なポイントとなります。
統合失調症で障害年金を受給するための3つの条件
統合失調症で障害年金を受給するためには、以下の3つの主要な条件をすべて満たす必要があります。
- 初診日要件:初めて医師の診療を受けた日が特定できること 「初診日」とは、統合失調症の症状により、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日を指します。この初診日にどの年金制度に加入していたかによって、支給される障害年金の種類が決まります。また、保険料納付要件を満たしているかの判断基準日にもなるため、初診日の特定と証明は非常に重要です。
- 保険料納付要件:年金保険料を一定期間納付していること 初診日の前々月までの公的年金の加入期間のうち、以下のいずれかを満たしている必要があります。
- 保険料納付済期間(免除・猶予・学生納付特例期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること。
- 初診日が令和8年3月31日以前にある場合は、初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと(特例)。
- ご自身の納付状況は、年金事務所や市区町村の年金窓口で確認できます。
- 障害状態要件:障害の程度が認定基準に該当すること 障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日、または症状が固定したと医師が判断した日)において、統合失調症による障害の程度が、国が定める障害等級に該当している必要があります。
精神の障害における障害等級の目安は以下の通りです。- 1級: 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの(他人の援助がなければほとんど自分の用事を済ませられない状態)。
- 2級: 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの(必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度)。
- 3級 (障害厚生年金のみ): 労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
- これらの等級は、医師が作成する診断書、ご本人やご家族が作成する「病歴・就労状況等申立書」などの内容を総合的に審査して決定されます。
統合失調症の障害年金申請における重要なポイント
統合失調症の障害年金申請には、特有の留意点があります。
- 症状の多様性と病識の有無の伝え方: 統合失調症の症状は多岐にわたり、時期によって現れ方が異なることもあります。陽性症状だけでなく、陰性症状や認知機能障害が日常生活や就労に与える影響を具体的に伝えることが重要です。また、ご本人に病識がない、または乏しい場合もあります。そのような場合は、ご家族や支援者の方が、ご本人の日常生活の状況や周囲から見た困難さを客観的に伝えることが求められます。
- 日常生活能力の的確な評価: 診断書には「日常生活能力の判定」という項目があり、食事、身辺の清潔保持、金銭管理、対人関係などの能力がどの程度あるかを医師が評価します。この評価は審査において非常に重視されるため、日頃からご自身の状態や困っていることを医師に正確に伝えておくことが大切です。具体的なエピソードを交えて説明すると、医師も状況を把握しやすくなります。
- 就労状況の正確な申告: 就労している場合でも、その事実だけで不支給となるわけではありません。仕事の種類、内容、勤務時間、収入、職場での配慮の状況(例えば、障害者雇用枠での就労、業務内容の軽減、頻繁な休憩など)を詳しく申告することが重要です。就労が不安定であったり、支援を受けながら何とか継続している状況なども、障害の程度を判断する上で考慮されます。
- 診断書の重要性と医師との良好な連携: 障害年金の審査において、医師が作成する「精神の障害用の診断書」は最も重要な書類の一つです。現在の症状だけでなく、発症からの経過、治療内容、日常生活や就労への支障について、医師に正確な情報を提供し、実態に即した診断書を作成してもらうことが不可欠です。ご家族からも医師に必要な情報を提供すると、より適切な診断書作成に繋がることがあります。
- 病歴・就労状況等申立書の丁寧な作成: 「病歴・就労状況等申立書」は、発病から現在までの経緯、症状の変化、治療の経過、日常生活や就労の状況をご本人やご家族が記載する書類です。診断書を補完し、ご本人の困難さを具体的に伝えるための重要な資料となります。特に統合失調症の場合、ご本人が詳細を記述することが難しい場合もあるため、ご家族のサポートを得ながら、できるだけ具体的に、矛盾なく記載することが求められます。
障害年金申請の流れ(統合失調症の場合)
統合失調症で障害年金を申請する際の一般的な手順は以下の通りです。ご本人の状態によっては、ご家族や支援者の協力が不可欠となることが多いです。
- 年金事務所・市区町村役場への相談: まずは最寄りの年金事務所や市区町村の年金窓口に相談し、障害年金制度の概要や申請に必要な書類(年金請求書、診断書様式など)について説明を受けます。初診日の確認や保険料納付要件についても確認しましょう。
- 初診日の証明書類の準備: 初診日を証明するための「受診状況等証明書」を、初診の医療機関に作成依頼します。これは、診断書を作成する医療機関と初診の医療機関が異なる場合に必要です。
- 医師への診断書作成依頼: 障害認定日以降に、主治医に「精神の障害用の診断書」の作成を依頼します。日常生活での困難さや就労に関する支障などをまとめたメモを事前に医師に渡しておくと、スムーズに作成が進むことがあります。
- 病歴・就労状況等申立書の作成: 発病から現在までの病状の経過、日常生活や就労の状況、家族からの援助の状況などを具体的に記載します。ご本人が作成困難な場合は、ご家族が代筆することも可能です。
- 年金請求書等の作成・提出: 年金請求書に必要事項を記入し、収集した診断書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書、その他必要書類(戸籍謄本、住民票、預金通帳の写しなど)を添えて、年金事務所または市区町村役場に提出します。
- 審査・結果通知: 提出された書類は日本年金機構で審査されます。審査期間は通常3ヶ月から半年程度ですが、状況により変動します。審査結果は書面で通知されます。
社労士に障害年金申請を依頼するメリット
統合失調症の障害年金申請は、ご本人やご家族にとって大きな負担となることがあります。専門家である社会保険労務士に申請代行を依頼することで、以下のようなメリットが期待できます。
- 煩雑な手続きの一任: 初診日の特定から書類の収集、作成、提出まで、複雑な手続きを専門家が代行します。
- 質の高い書類作成: 認定基準や審査のポイントを熟知しているため、受給可能性を高めるための適切な書類作成をサポートします。特に、ご本人の状態を正確に伝える「病歴・就労状況等申立書」の作成支援は大きな助けとなります。
- 年金事務所とのスムーズな対応: 専門家として、年金事務所からの照会や追加の求めにも的確に対応します。
- 受給可能性の向上: 豊富な知識と経験に基づき、個々のケースに最適な申請戦略を立てることで、受給の可能性を高めます。
- ご本人・ご家族の負担軽減: 手続きの負担や精神的なストレスを軽減し、治療や日常生活に専念できる環境を整えるお手伝いをします。特にご本人が申請手続きを行うことが困難な場合、ご家族の負担も大きく軽減できます。
統合失調症の障害年金に関するよくある質問
Q1. 症状が落ち着いている時期がありますが、申請できますか?
A1. 統合失調症の症状には波があることが一般的です。症状が一時的に落ち着いている時期があっても、全体として日常生活や就労に支障があれば申請可能です。申請書類には、症状が良い時期と悪い時期それぞれの状況を具体的に記載することが大切です。
Q2. 入院歴がないと不利ですか?
A2. 入院歴の有無だけで障害の程度が判断されるわけではありません。通院治療のみでも、症状によって日常生活や就労に大きな支障があれば、障害年金の対象となります。重要なのは、現在の障害の状態です。
Q3. 家族が代わりに申請手続きをできますか?
A3. はい、可能です。ご本人が申請手続きを行うことが困難な場合は、ご家族が代理で手続きを進めることができます。病歴・就労状況等申立書なども、ご家族がご本人の状況を把握した上で記載することが認められています。
Q4. 働いていても受給できますか?
A4. 就労している場合でも、仕事内容、勤務時間、収入、職場での援助や配慮の状況などを総合的に考慮して障害の程度が判断されます。一般雇用であっても、かなりの配慮を受けていたり、短時間勤務であったりする場合などは、受給の可能性があります。
Q5. もし不支給になった場合、どうすれば良いですか?
A5. 障害年金の請求が認められなかったり、決定された等級に納得がいかない場合は、結果を知った日の翌日から3ヶ月以内に「審査請求」という不服申し立てを行うことができます。諦めずに、まずは専門家にご相談ください。
ご相談は静岡障害年金サポートきぼうへ
統合失調症を抱えながらの生活は、ご本人にとってもご家族にとっても、多くの困難を伴うことと思います。障害年金は、そうした方々の経済的な基盤を支え、安心して治療に専念したり、自分らしい生活を送るための一助となる大切な制度です。
「自分は対象になるのだろうか」「手続きが難しそう」と感じている方も、どうか一人で悩まず、障害年金申請の専門家である社会保険労務士にご相談ください。当事務所では、統合失調症の特性を理解し、お一人おひとりの状況に寄り添いながら、最適な申請方法をご提案し、受給に向けて全力でサポートいたします。
この記事が、統合失調症で障害年金をお考えの方々にとって、確かな情報と希望をお届けできれば幸いです。
プロフィール

- 社会保険労務士
-
ご覧いただきありがとうございます。
三島市・富士市・沼津市・熱海市・伊豆全域・御殿場中心に
静岡県全域の障害年金の請求サポートをしております。
障害年金について気になることやご質問があれば
お気軽にご相談ください。
一人でも多くの方が明るい未来へと歩み出せるよう、
全力でサポートいたします。
最新の投稿
- 7月 7, 2025コラム障害年金の遡及請求とは?過去分の受給可能性と申請ポイントを社労士が解説
- 7月 7, 2025コラム働きながら障害年金はもらえる?受給の可否を左右するポイントを社労士が解説
- 7月 7, 2025コラムがんで障害年金はもらえる?ステージ・治療中の申請ポイントを社労士が解説
- 7月 7, 2025コラム人工透析で障害年金はもらえる?等級2級の基準・申請時期を社労士が解説
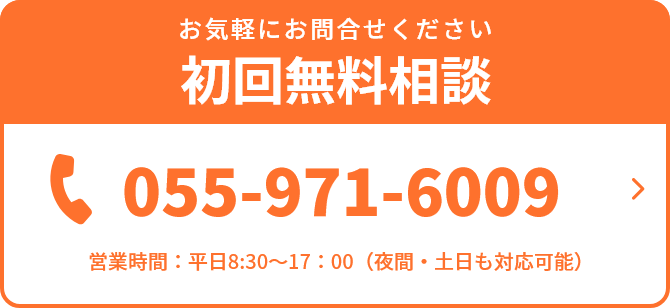
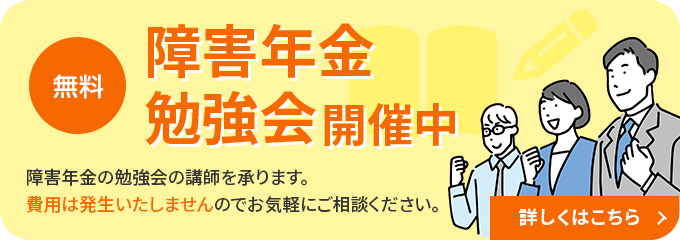

 初めての方へ
初めての方へ