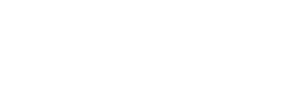双極性障害で障害年金は受給できる?気分の波と申請ポイントを社労士が解説
目次
「気分の浮き沈みが激しく、自分でもコントロールできない」「躁状態の時は活動的すぎるほどだが、うつ状態になると何も手につかない」…。双極性障害(かつての躁うつ病)は、このような気分の極端な波を繰り返す精神疾患であり、ご本人だけでなくご家族の生活にも大きな影響を与えることがあります。
仕事や学業、人間関係がうまくいかず、将来への経済的な不安を感じたり、治療に専念したいけれど生活費が心配だったりする方も少なくないでしょう。そのような状況において、経済的な支えとなり得るのが「障害年金」です。
しかし、「躁の時は元気に見えるけど、障害年金をもらえるの?」「気分の波があることをどう伝えればいいの?」といった疑問や不安をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
この記事では、障害年金申請代行を専門とする社会保険労務士が、双極性障害で障害年金を受給するための条件、申請手続の流れ、そして双極性障害特有の申請における重要なポイントや注意点について、詳しく解説します。
この記事を通じて、双極性障害と向き合いながら生活されているご本人、そしてそのご家族が障害年金制度への理解を深め、経済的な安心を得るための一助となれば幸いです。
双極性障害と障害年金の基礎知識
まず、障害年金制度の概要と、双極性障害がどのように障害年金の対象となるのかについてご説明します。
障害年金とは?
障害年金は、病気やケガによって法律で定められた障害の状態になった場合に支給される公的な年金です。初診日に加入していた年金制度に応じて、主に以下の2種類があります。
- 障害基礎年金: 初診日に国民年金に加入していた方(自営業者、専業主婦(夫)、学生、無職の方など)、または20歳前に初診日がある方が対象です。障害等級は1級と2級です。
- 障害厚生年金: 初診日に厚生年金に加入していた方(会社員や公務員など)が対象です。障害基礎年金に上乗せして支給され、障害等級は1級から3級まであります。3級よりも軽い障害状態の場合には障害手当金(一時金)が支給されることもあります。
双極性障害も障害年金の対象です
双極性障害は、「精神の障害」として障害年金の支給対象となります。「気分(感情)障害」の認定基準に基づいて、躁状態やうつ状態、あるいはそれらが混在する混合状態が、日常生活や社会生活(仕事、家事、対人関係など)にどれほどの支障を生じさせているかが総合的に審査されます。
双極性障害の主な症状:
- 躁状態: 気分が高揚し、異常に活動的になる。眠らなくても平気になったり、多弁になったり、次々とアイデアが浮かんだりする一方で、注意散漫になったり、浪費を繰り返したり、些細なことで激怒したりするなど、社会生活に支障をきたす行動が見られることがあります。
- うつ状態: 気分が落ち込み、興味や喜びを感じられなくなる。不眠または過眠、食欲不振または過食、気力・集中力の低下、自己否定感、希死念慮などが現れます。
- 混合状態: 躁状態とうつ状態の症状が同時に、または急速に交替して現れる状態。
これらの気分の波が、ご本人の意思とは関係なく現れ、生活全般に大きな影響を与える点が双極性障害の大きな特徴です。
双極性障害で障害年金を受給するための条件
双極性障害で障害年金を受給するためには、主に以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
- 初診日要件:双極性障害の症状により初めて医師の診療を受けた日が特定できること 「初診日」とは、双極性障害の症状(躁状態、うつ状態のいずれでも可)により、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日を指します。
- 診断名変更のケース: 最初はうつ病と診断されていたが、その後の経過で双極性障害と診断名が変更になった場合でも、最初のうつ症状で医療機関を受診した日が初診日と認められることが一般的です。
- この初診日にどの年金制度に加入していたかによって、支給される障害年金の種類が決まります。
- 保険料納付要件:年金保険料を一定期間納付していること 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間のうち、以下のいずれかを満たしている必要があります。
- 保険料納付済期間(免除・猶予・学生納付特例期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること。
- 初診日が令和8年3月31日以前にある場合は、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと(特例)。 (20歳前に初診日がある場合は、この納付要件は問われません)
- 障害状態要件:障害の程度が認定基準に該当すること 障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日)において、双極性障害による障害の程度が、国が定める障害等級に該当している必要があります。 双極性障害の認定では、症状の重さだけでなく、その症状によって日常生活や就労にどれだけの支障が生じているかが重視されます。気分の波があるため、症状が良い時期と悪い時期の状況を総合的に評価し、全体としてどの程度の支障があるかで判断されます。
- 1級: 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。
- 2級: 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
- 3級 (障害厚生年金のみ): 労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
双極性障害の障害年金申請における重要なポイント
双極性障害の障害年金申請では、その特有の症状の波をいかに的確に伝えるかが鍵となります。
- 気分の波(躁状態・うつ状態)の具体的な申告:
- 「躁状態の時は元気そうに見える」と誤解されがちですが、その行動が社会生活上の問題(浪費、人間関係のトラブル、仕事での無責任な行動など)を引き起こし、結果的に本人を苦しめていることを具体的に示す必要があります。
- うつ状態の時の無気力さ、引きこもり、希死念慮などの深刻さも詳細に伝えます。
- 症状が良い時期(寛解期)があっても、それが持続せず、再び気分の波に襲われる不安定さを明確にすることが重要です。日常生活や就労の状況を、症状の波と関連付けて記述しましょう。
- 日常生活能力・社会生活能力・就労能力への影響の具体化:
- 気分の波によって、計画的な行動ができない、集中力や判断力が著しく低下する、対人関係を円滑に維持できない、安定した就労が困難である、などの状況を具体的にエピソードを交えて説明します。
- 躁状態の時の衝動的な行動(例:多額の借金をしてしまう、無謀な事業計画を立ててしまう、頻繁に転職を繰り返すなど)が、その後の生活にどのような悪影響を及ぼしているかも重要な情報です。
- 治療歴と服薬状況の正確な記録:
- これまでの治療経過(通院歴、入院歴、試した薬剤の種類や量、効果、副作用など)を時系列で整理して伝えることが大切です。治療によっても気分の波が十分にコントロールできず、生活に支障が出ていることを示します。
- 診断書の内容 ― 医師との連携が不可欠:
- 診断書は審査において最も重視される書類の一つです。医師に、これまでの気分の波のパターン(周期、各エピソードの期間・重症度)、躁状態・うつ状態それぞれの具体的な症状、それらが日常生活や就労、対人関係に与えている影響を正確に伝え、診断書に反映してもらうことが極めて重要です。
- 診断名が途中でうつ病から双極性障害に変更になった場合は、その経緯も医師に伝え、診断書にその旨を記載してもらうとスムーズです。
- 病歴・就労状況等申立書の丁寧な作成:
- この書類は、ご本人やご家族が、発症から現在までの気分の波の具体的なエピソード、それによって生じた生活上・仕事上の困難さ、治療の経過などを時系列で詳細に記述するものです。
- 躁状態の時の行動や、うつ状態の時の状況を、できるだけ客観的に、具体的に記載します。家族や周囲の人から見た状況を補足することも有効です。
- 日本年金機構が公表している「気分(感情)障害の認定に関するガイドライン」を意識し、症状の持続性や頻度、日常生活への影響度などを盛り込むと、より審査員に伝わりやすくなります。
障害年金申請の流れ(双極性障害の場合)
基本的な申請の流れは他の傷病と同様ですが、双極性障害の場合、症状の波があるため、診断書を依頼するタイミングや、申立書に症状の変動をどう記述するかがポイントとなります。
- 年金事務所・市区町村役場への相談: 制度の概要や必要書類を確認します。
- 初診日の確認・証明書類の準備: 初診の医療機関から「受診状況等証明書」を取得します。
- 医師への診断書作成依頼: 現在の主治医に依頼します。症状が悪い時期だけでなく、良い時期も含めた全体像を医師に伝えることが重要です。
- 病歴・就労状況等申立書の作成: 気分の波とそれに伴う生活の変化を具体的に記載します。
- 年金請求書等の作成・提出: 必要書類を揃えて提出します。
- 審査・結果通知: 通常3ヶ月~半年程度かかります。
社労士に障害年金申請を依頼するメリット
双極性障害の障害年金申請は、症状の波を的確に伝え、それが日常生活や就労に継続的な支障を与えていることを客観的に示す必要があり、専門的な知識と経験が求められます。社会保険労務士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。
- 双極性障害特有の症状の波を的確に伝える書類作成のサポート。
- 初診日の特定(診断名が変更されたケースなど)に関する的確なアドバイス。
- 躁状態での行動など、デリケートな情報も適切に整理し、審査に配慮した形での申告をサポート。
- 「気分(感情)障害の認定に関するガイドライン」を踏まえた申請書類の作成支援。
- 煩雑な手続きの代行による、ご本人やご家族の精神的・時間的負担の軽減。
- 障害年金の専門家として、受給の可能性を高めるための最適な申請戦略の提案。
双極性障害の障害年金に関するよくある質問
Q1. 躁状態の時は元気に見えるのですが、障害年金の対象になりますか?
A1. はい、対象となる可能性があります。躁状態であっても、その行動が衝動的であったり、社会的な問題を引き起こしたりするなど、結果的にご本人にとって不利益な状況を生み出し、日常生活や社会生活に支障をきたしていれば、障害の程度として評価されます。大切なのは、気分の波全体を通して、生活にどれだけの困難があるかです。
Q2. 最初はうつ病と診断されていましたが、後から双極性障害と診断が変わりました。初診日はいつになりますか?
A2. 一般的には、最初にうつ症状で医療機関を受診した日が初診日と認められることが多いです。診断名が変わったとしても、一連の気分障害の症状として扱われるためです。
Q3. 気分の波が激しくて仕事が続きません。この点は考慮されますか?
A3. はい、非常に重要な評価ポイントです。気分の波によって安定した就労が困難であること、転職を繰り返したり、休職が多かったりする状況は、労働能力に制約があると判断される有力な材料となります。
Q4. 症状が良い時期もありますが、申請できますか?
A4. はい、申請できます。双極性障害は症状に波があることが前提の疾患です。症状が良い時期があるからといって、直ちに不支給となるわけではありません。症状の波全体を通じて、日常生活や社会生活にどれだけの制約があるかが総合的に評価されます。
Q5. 浪費や借金など、躁状態の時の問題行動も伝えるべきですか?
A5. はい、伝えるべきです。躁状態の時の浪費や借金、対人関係のトラブルなどは、病状による判断力の低下や衝動性の高まりを示す重要な情報であり、障害の程度を評価する上で考慮されます。ただし、伝え方には配慮が必要なため、専門家にご相談いただくことをお勧めします。
ご相談は静岡障害年金サポートきぼうへ
双極性障害の激しい気分の波は、ご本人にとって非常につらく、コントロールが難しいものです。経済的な不安が少しでも軽減されれば、安心して治療に専念し、病状の安定や社会復帰を目指す上での大きな助けとなります。
「自分の状態をうまく説明できるだろうか」「こんなことで申請してもいいのだろうか」と悩んでいる方も、どうか諦めずに、一度、障害年金専門の社会保険労務士にご相談ください。
当事務所では、双極性障害の特性や、それに伴う特有の困難さを深く理解し、お一人おひとりの状況に寄り添いながら、障害年金の受給に向けて全力でサポートいたします。
この記事が、双極性障害と闘うあなたとご家族にとって、確かな情報と希望をお届けできれば幸いです。
プロフィール

- 社会保険労務士
-
ご覧いただきありがとうございます。
三島市・富士市・沼津市・熱海市・伊豆全域・御殿場中心に
静岡県全域の障害年金の請求サポートをしております。
障害年金について気になることやご質問があれば
お気軽にご相談ください。
一人でも多くの方が明るい未来へと歩み出せるよう、
全力でサポートいたします。
最新の投稿
- 7月 7, 2025コラム障害年金の遡及請求とは?過去分の受給可能性と申請ポイントを社労士が解説
- 7月 7, 2025コラム働きながら障害年金はもらえる?受給の可否を左右するポイントを社労士が解説
- 7月 7, 2025コラムがんで障害年金はもらえる?ステージ・治療中の申請ポイントを社労士が解説
- 7月 7, 2025コラム人工透析で障害年金はもらえる?等級2級の基準・申請時期を社労士が解説
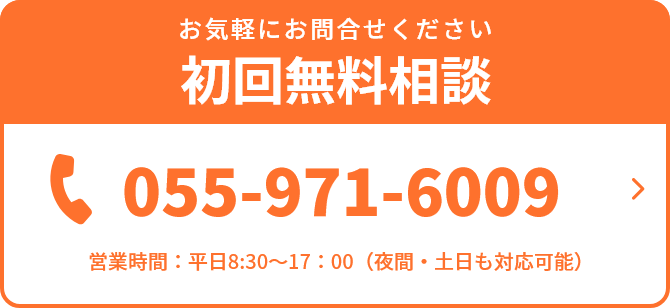
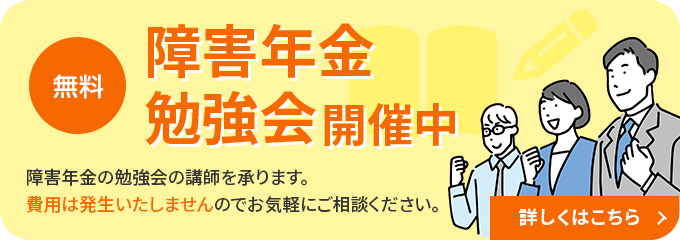

 初めての方へ
初めての方へ