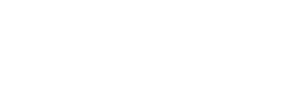脳梗塞の後遺症で障害年金はもらえる?申請時期・等級・注意点を社労士が解説
目次
ある日突然襲ってくる脳梗塞。一命を取り留めたとしても、麻痺や言語障害、記憶力の低下といった後遺症が残り、以前と同じような生活を送ることが難しくなるケースは少なくありません。ご本人やご家族は、先の見えない不安や、経済的な心配を抱えていらっしゃることでしょう。
そのような状況で、療養生活やリハビリを支える経済的な基盤の一つとなるのが「障害年金」です。脳梗塞の後遺症により、日常生活や仕事に支障が出ている場合、障害年金を受給できる可能性があります。
「脳梗塞になったら、どんな後遺症でもらえるの?」「リハビリ中だけど申請できる?」「いつ申請するのがベストなの?」
この記事では、障害年金申請代行を専門とする社会保険労務士が、脳梗塞の後遺症で障害年金を受給するための条件、後遺症の評価、申請のタイミングや注意点について、詳しく解説します。
この記事が、脳梗塞とその後遺症に向き合う皆様にとって、少しでも希望の光となり、経済的な不安を和らげるための一助となれば幸いです。
脳梗塞と障害年金の基礎知識
まず、障害年金制度の基本的な仕組みと、脳梗塞の後遺症がどのように障害年金の対象となるのかについてご説明します。
障害年金とは?
障害年金は、病気やケガによって法律で定められた障害の状態になった場合に支給される公的な年金です。初診日に加入していた年金制度に応じて、主に以下の2種類があります。
- 障害基礎年金: 初診日に国民年金に加入していた方(自営業者、専業主婦(夫)、学生、無職の方など)、または20歳前に初診日がある方が対象です。障害等級は1級と2級です。
- 障害厚生年金: 初診日に厚生年金に加入していた方(会社員や公務員など)が対象です。障害基礎年金に上乗せして支給され、障害等級は1級から3級まであります。3級よりも軽い障害状態の場合には障害手当金(一時金)が支給されることもあります。
脳梗塞の後遺症も障害年金の対象です
脳梗塞の後遺症は、その種類や程度によって、「神経系統の機能又は精神の障害」や「肢体の機能の障害」など、複数の障害認定基準に該当する可能性があります。
脳梗塞によって生じうる主な後遺症と、障害年金における評価の視点:
- 運動機能障害(片麻痺など): 手足の麻痺の範囲や程度、それによる日常生活動作(食事、入浴、着替え、歩行など)への支障の度合い。
- 言語機能障害(失語症など): 「聞く」「話す」「読む」「書く」といった言語能力がどの程度障害されているか。
- 高次脳機能障害: 記憶障害(新しいことを覚えられない、過去の出来事を思い出せない)、注意障害(集中力が続かない、周囲の刺激に気を取られやすい)、遂行機能障害(計画を立てて物事を実行できない)、社会的行動障害(感情のコントロールが難しい、状況に合わない行動をとる)など、目に見えにくいこれらの障害が日常生活や社会生活に与える影響。
- その他の障害: 視野障害、嚥下障害なども評価の対象となります。
これらの後遺症が単独または複数存在し、日常生活や労働に支障をきたしている場合に、障害年金の受給が検討されます。
脳梗塞の後遺症で障害年金を受給するための条件
脳梗塞の後遺症で障害年金を受給するためには、主に以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
- 初診日要件:脳梗塞で初めて医師の診療を受けた日が特定できること 「初診日」とは、脳梗塞の症状(手足のしびれ、ろれつが回らない、意識障害など)により、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日を指します。救急搬送された場合は、その搬送先の医療機関で診療を受けた日が初診日となることが一般的です。
- 保険料納付要件:年金保険料を一定期間納付していること 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間のうち、以下のいずれかを満たしている必要があります。
- 保険料納付済期間(免除・猶予・学生納付特例期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること。
- 初診日が令和8年3月31日以前(※執筆時点2025年5月8日のため、将来の日付となっていますが、現行の特例に基づいています)にある場合は、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと(特例)。 (20歳前に初診日がある場合は、この納付要件は問われません)
- 障害状態要件:障害の程度が認定基準に該当すること 脳梗塞の後遺症による障害の程度は、原則として**「症状固定」後、または初診日から1年6ヶ月を経過した日(障害認定日)**の状態で判断されます。
- 症状固定とは: 脳梗塞発症後、急性期治療やリハビリテーションを行っても、それ以上症状の改善が見込めないと医学的に判断された状態を指します。
- 障害認定日:
- 原則:初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日。
- 特例:1年6ヶ月以内であっても、医師が症状固定と診断した場合は、その日が障害認定日となります。ただし、脳梗塞発症から6ヶ月未満で症状固定と診断されるケースは稀で、多くは6ヶ月以上のリハビリ期間を経て判断されます。 この障害認定日において、後遺症の程度が国が定める障害等級に該当している必要があります。
- 後遺症の種類に応じた評価:
- 肢体の障害: 上肢・下肢の機能障害の程度(用を全廃したもの、著しい障害を有するもの、軽度の障害を有するものなど)や、体幹・脊柱の機能障害の程度に応じて等級が判断されます。日常生活動作(ADL)の状況が重視されます。
- 言語機能の障害: そしゃく・嚥下機能、音声・言語機能の障害の程度に応じて等級が判断されます。「話すこと」「聞くこと」の能力がどの程度残存しているかがポイントです。
- 精神の障害(高次脳機能障害を含む): 高次脳機能障害による能力低下の程度や、それが日常生活や社会生活に及ぼす影響の度合い(意思疎伝能力、問題解決能力、作業負荷への耐性、対人関係など)を総合的に評価します。
- 併合認定: 複数の後遺症がある場合(例:右半身麻痺と言語障害)、それぞれの障害の程度を評価し、それらを組み合わせて全体の障害等級が決定される「併合(加重)認定」という仕組みがあります。
脳梗塞の障害年金申請における重要なポイント
脳梗塞の後遺症で障害年金を申請する際には、以下の点が特に重要になります。
- 申請のタイミング(障害認定日)と「症状固定」の理解:
- 脳梗塞発症後、すぐに障害年金を申請できるわけではありません。原則として、初診日から1年6ヶ月経過を待つか、それ以前に医師から「症状固定」の診断を受ける必要があります。
- 急性期病院からリハビリ病院へ転院し、集中的なリハビリテーションを受ける方が多いですが、その効果や症状の安定を見極める期間が必要です。主治医とよく相談し、症状固定の時期や障害年金申請のタイミングについて助言を得ましょう。
- 診断書の適切な作成依頼: 後遺症の種類によって、使用する診断書の様式が異なります。
- 肢体の障害用(様式第120号の1): 麻痺の範囲、関節可動域、筋力、日常生活動作(ADL)の具体的な状況(介助の要否など)を詳細に記載してもらう必要があります。
- 精神の障害用(様式第120号の4): 高次脳機能障害の場合に主に使用します。記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害の具体的な症状や、日常生活・社会生活への支障、神経心理学的検査の結果などを記載してもらいます。ご家族から日常生活での具体的なエピソードを医師に伝えることも非常に重要です。
- 言語機能の障害用(様式第120号の5): 失語症などの場合に、発語、聴取、読解、書字の能力について記載してもらいます。 場合によっては複数の診断書が必要になることもあります。医師に後遺症の全体像を正確に伝え、適切な診断書を作成してもらうことが不可欠です。
- 病歴・就労状況等申立書の詳細な記述: この書類は、発症前の健康状態、脳梗塞発症時の状況、治療やリハビリの経過、そして現在の後遺症によって日常生活や就労にどのような支障が出ているかを、ご自身の言葉で具体的に記載するものです。
- 特に高次脳機能障害のような「見えにくい障害」については、具体的なエピソード(例:約束を忘れてしまう、作業の手順が分からなくなる、感情の起伏が激しくなったなど)を交えて、いかに生活が困難になっているかを審査員に理解してもらう必要があります。
- ご本人が記述が難しい場合は、ご家族や介護者が協力して作成することが重要です。
- リハビリテーションの状況と今後の見通し: どのようなリハビリテーションをどれくらいの期間受けたか、その効果はどうだったか、リハビリ終了後の生活や就労の見通しなども、申立書に記載するとよいでしょう。
障害年金申請の流れ(脳梗塞の後遺症の場合)
脳梗塞の後遺症による障害年金申請の一般的な流れは以下の通りです。
- 年金事務所・市区町村役場への相談: まずは制度の概要や必要書類を確認します。
- 初診日の確認・証明書類の準備: 脳梗塞で最初に受診した医療機関から「受診状況等証明書」を取得するなどして初診日を証明します。
- 医師への診断書作成依頼: 症状固定後、または障害認定日以降に、後遺症に応じた診断書の作成を主治医に依頼します。
- 病歴・就労状況等申立書の作成: ご自身の状況を具体的に、かつ分かりやすく記載します。
- 年金請求書等の作成・提出: 必要書類を揃えて年金事務所または市区町村役場に提出します。
- 審査・結果通知: 通常3ヶ月~半年程度かかります。
社労士に障害年金申請を依頼するメリット
脳梗塞の後遺症は多岐にわたり、申請準備も複雑になることがあります。社会保険労務士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。
- 後遺症の多様性に応じた適切なアドバイスと申請戦略の立案。
- 症状固定の時期や障害認定日に関する的確な判断サポート。
- 複数の診断書が必要な場合の調整や、医師への依頼時のポイント伝達。
- 高次脳機能障害のような「見えにくい障害」を効果的に伝えるための書類作成支援。
- 煩雑な手続きの代行による、ご本人やご家族の精神的・時間的負担の軽減。
- 障害年金の専門家として、受給の可能性を高めるための最適なサポート。
脳梗塞の障害年金に関するよくある質問
Q1. 脳梗塞で倒れてすぐでも障害年金を申請できますか?
A1. 原則としてすぐには申請できません。脳梗塞の後遺症による障害年金は、症状が固定したと医師が判断した後、または初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)の状態に基づいて審査されます。まずは治療とリハビリに専念することが大切です。
Q2. リハビリを続けていますが、いつ申請するのが良いですか?「症状固定」とは何ですか?
A2. 主治医と相談し、「症状固定」(これ以上リハビリを続けても大幅な改善が見込めない状態)と判断された時点、または初診日から1年6ヶ月が経過した時点が申請の目安となります。どちらか早い方が障害認定日となります(ただし、初診日から6ヶ月未満での症状固定は稀です)。
Q3. 片麻痺だけでなく、記憶力も低下しました。両方とも評価されますか?
A3. はい、評価されます。片麻痺(肢体の障害)と記憶障害(精神の障害・高次脳機能障害)は、それぞれ別の障害として評価され、最終的にそれらを総合した障害の程度(併合等級)で認定されることがあります。それぞれの後遺症について、適切な診断書を提出することが重要です。
Q4. 働いていても障害年金はもらえますか?
A4. 働いているという理由だけで不支給になるわけではありません。後遺症のために仕事内容に大きな制約があったり、職場からの特別な配慮が必要であったり、以前のように働くことが困難であったりする場合には、受給できる可能性があります。特に障害厚生年金3級は、一定の就労をしながらも労働能力に著しい制限がある状態が対象となります。
Q5. 障害者手帳を持っていますが、障害年金ももらえますか?等級は同じですか?
A5. 障害者手帳と障害年金は別の制度ですので、障害者手帳を持っていても、別途障害年金の申請が必要です。また、それぞれの制度で等級の認定基準が異なるため、障害者手帳の等級と障害年金の等級が必ずしも一致するわけではありません。
ご相談は静岡障害年金サポートきぼうへ
脳梗塞の発症は、ご本人にとってもご家族にとっても大変な出来事です。後遺症と向き合いながらの生活は、精神的にも肉体的にも、そして経済的にも大きな負担を伴うことがあります。障害年金は、そのような状況下で療養生活を支えるための大切な制度です。
後遺症の種類や程度、申請のタイミングなど、専門的な判断が必要となる場面も多いため、一人で悩まず、まずは障害年金専門の社会保険労務士にご相談ください。
当事務所では、脳梗塞の後遺症に苦しむ方々の状況を丁寧に伺い、障害年金の受給に向けて最適なサポートを提供いたします。
この記事が、皆様の不安を少しでも和らげ、希望を持って次の一歩を踏み出すためのお手伝いとなれば幸いです。
プロフィール

- 社会保険労務士
-
ご覧いただきありがとうございます。
三島市・富士市・沼津市・熱海市・伊豆全域・御殿場中心に
静岡県全域の障害年金の請求サポートをしております。
障害年金について気になることやご質問があれば
お気軽にご相談ください。
一人でも多くの方が明るい未来へと歩み出せるよう、
全力でサポートいたします。
最新の投稿
- 7月 7, 2025コラム障害年金の遡及請求とは?過去分の受給可能性と申請ポイントを社労士が解説
- 7月 7, 2025コラム働きながら障害年金はもらえる?受給の可否を左右するポイントを社労士が解説
- 7月 7, 2025コラムがんで障害年金はもらえる?ステージ・治療中の申請ポイントを社労士が解説
- 7月 7, 2025コラム人工透析で障害年金はもらえる?等級2級の基準・申請時期を社労士が解説
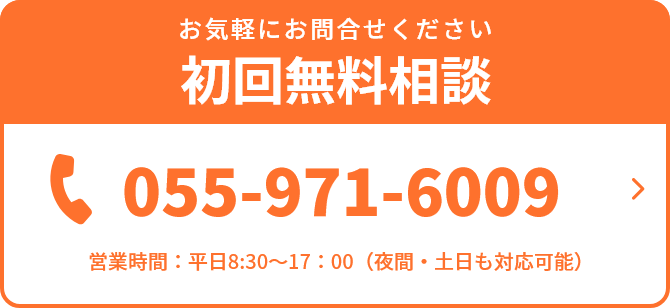
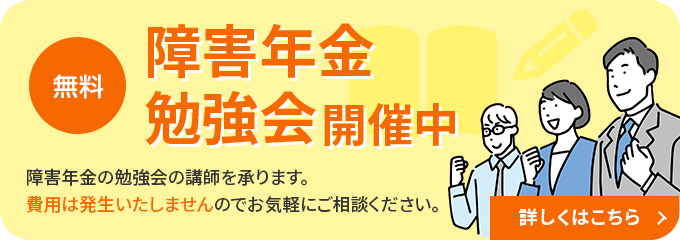

 初めての方へ
初めての方へ