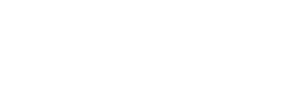糖尿病で障害年金はもらえる?合併症の基準・等級・申請ポイントを社労士が解説
目次
糖尿病と診断され、食事療法や運動療法、薬物治療(インスリン注射を含む)を長年続けていらっしゃる方。そして、残念ながら糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害といった合併症を発症し、日常生活や仕事に大きな支障が出ている方も少なくないでしょう。
「糖尿病だけでも障害年金はもらえるの?」「合併症がないとダメなの?」「人工透析になったらどうなるの?」
こうした疑問や経済的な不安を抱えている方もいらっしゃると思います。糖尿病そのもので障害年金を受給することは原則として難しいですが、糖尿病が原因で重い合併症を発症し、それによって生活や仕事が著しく制限される場合には、障害年金を受給できる可能性があります。
この記事では、障害年金申請代行を専門とする社会保険労務士が、糖尿病とその合併症で障害年金を受給するための条件、合併症ごとの認定基準、申請のタイミングや注意点について、詳しく解説します。
この記事が、糖尿病とその合併症と向き合いながら生活されている皆様にとって、障害年金制度への理解を深め、経済的な安心を得るための一助となれば幸いです。
糖尿病と障害年金の基礎知識
まず、障害年金制度の概要と、糖尿病とその合併症がどのように障害年金の対象となるのかについてご説明します。
障害年金とは?
障害年金は、病気やケガによって法律で定められた障害の状態になった場合に支給される公的な年金です。初診日に加入していた年金制度に応じて、主に以下の2種類があります。
- 障害基礎年金: 初診日に国民年金に加入していた方(自営業者、専業主婦(夫)、学生、無職の方など)、または20歳前に初診日がある方が対象です。障害等級は1級と2級です。
- 障害厚生年金: 初診日に厚生年金に加入していた方(会社員や公務員など)が対象です。障害基礎年金に上乗せして支給され、障害等級は1級から3級まであります。3級よりも軽い障害状態の場合には障害手当金(一時金)が支給されることもあります。
糖尿病とその合併症は障害年金の対象です
糖尿病は、それ自体が直接的に障害年金の支給対象となることは原則としてありません。なぜなら、糖尿病は適切な治療や生活習慣の改善によって血糖コントロールが可能であり、多くの場合は日常生活や労働に大きな支障なく生活できると考えられているためです。
しかし、糖尿病が進行し、以下のような重篤な合併症を発症し、それによって日常生活や労働能力が著しく損なわれた場合には、その合併症による障害として障害年金の対象となります。
- 糖尿病性網膜症: 視力の低下、視野の狭窄、最悪の場合は失明に至ることもあります。「眼の障害」として評価されます。
- 糖尿病性腎症: 腎機能が低下し、進行すると末期腎不全となり人工透析が必要になります。「腎疾患による障害」として評価されます。
- 糖尿病性神経障害: 手足のしびれや痛み、感覚麻痺、筋力低下、自律神経障害(立ちくらみ、排尿障害、消化器症状など)が現れます。重症化すると足の潰瘍や壊疽を引き起こし、下肢切断に至ることもあります。「肢体の機能の障害」や「神経系統の機能又は精神の障害」として評価されます。
- その他: 糖尿病は心筋梗塞や脳梗塞などの心血管疾患のリスクも高めます。これらの疾患による後遺症も障害年金の対象となり得ます。
糖尿病で障害年金を受給するための条件(主に合併症による)
糖尿病の合併症で障害年金を受給するためには、主に以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
- 初診日要件:原則として「糖尿病」で初めて医師の診療を受けた日が特定できること ここが非常に重要なポイントです。「初診日」とは、障害の原因となった傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日を指します。糖尿病の合併症で障害年金を請求する場合、原則として合併症の症状で初めて受診した日ではなく、その原因である「糖尿病」で初めて医師の診療を受けた日が初診日となります。
- 保険料納付要件:年金保険料を一定期間納付していること (糖尿病の)初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間のうち、以下のいずれかを満たしている必要があります。
- 保険料納付済期間(免除・猶予・学生納付特例期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること。
- 初診日が令和8年3月31日以前(※執筆時点2025年5月8日のため、現行の特例に基づいています)にある場合は、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと(特例)。 (20歳前に糖尿病の初診日がある場合は、この納付要件は問われません)
- 障害状態要件:合併症による障害の程度が認定基準に該当すること 障害認定日(詳細は後述)において、糖尿病の合併症による障害の程度が、国が定める障害等級に該当している必要があります。主な合併症の認定基準の目安は以下の通りです。
- 糖尿病性網膜症(眼の障害):
- 矯正視力や視野の程度によって評価されます。例えば、両眼の視力の和が0.04以下のものは1級、0.05以上0.08以下のものは2級などと定められています。
- 糖尿病性腎症(腎疾患による障害):
- 人工透析療法を受けている場合:原則として2級に認定されます。
- 人工透析を受けていない場合でも、腎機能の検査値(血清クレアチニン濃度、eGFRなど)や全身状態、日常生活の支障の程度によって1級、2級、3級に該当する可能性があります。
- 糖尿病性神経障害(肢体の機能の障害など):
- 上肢または下肢の機能障害の程度(麻痺の範囲、関節可動域、筋力、歩行能力、日常生活動作への支障など)によって評価されます。
- 下肢の切断に至った場合は、切断部位や両下肢か片下肢かによって等級が異なります。
- 代謝障害としての評価(極めて稀なケース): インスリン治療を長期間行ってもなお血糖コントロールが極めて不良で、かつ全身状態が著しく悪く、日常生活や労働に高度な支障がある場合には、「代謝疾患による障害」として認定される可能性も理論上はありますが、認定のハードルは非常に高いです。
- 併合認定: 複数の合併症がある場合(例:糖尿病性網膜症と糖尿病性腎症)、それぞれの障害の程度を評価し、それらを組み合わせて全体の障害等級が決定される「併合(加重)認定」という仕組みがあります。
- 糖尿病性網膜症(眼の障害):
糖尿病(合併症)の障害年金申請における重要なポイント
糖尿病の合併症で障害年金を申請する際には、以下の点が特に重要になります。
- 申請のタイミング(障害認定日)の確認: 障害認定日は、原則として(糖尿病の)初診日から1年6ヶ月を経過した日です。ただし、合併症の種類によっては特例があります。
- 人工透析療法を開始した場合: 透析を初めて受けた日から起算して3ヶ月を経過した日。
- 肢体を切断した場合: 原則として切断した日(医学的に切断が必要と認められる状態になった日)。
- その他(網膜症、神経障害など): 原則通り初診日から1年6ヶ月後、またはそれ以前に症状が固定したと医師が判断した日。
- 診断書の適切な作成依頼: 合併症の種類に応じて、使用する診断書の様式が異なります。
- 糖尿病性網膜症: 「眼の障害用」(様式第120号の2)
- 糖尿病性腎症(人工透析を含む): 「腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用」(様式第120号の6-(2))
- 糖尿病性神経障害・足病変による肢体障害: 「肢体の障害用」(様式第120号の1) いずれの診断書にも、糖尿病の治療歴(インスリン治療の有無、期間、血糖コントロール状況、HbA1cの推移など)や、合併症の発症時期・進行状況、現在の症状、検査所見、日常生活への支障などを具体的に記載してもらう必要があります。ご自身の困っている状況を正確に医師に伝えることが極めて重要です。
- 病歴・就労状況等申立書の詳細な記述: この書類は、糖尿病の発症(初診)から現在までの治療の経緯、血糖コントロールのための努力、合併症の発症と進行の状況、そしてそれによって日常生活や就労にどのような支障が出ているかを、ご自身の言葉で具体的に、時系列に沿って記載するものです。
- 食事療法、運動療法、薬物療法(インスリン治療を含む)をどのように行ってきたか。
- 合併症によってどのような症状が現れ、生活のどの場面で困っているか(例:視力低下で文字が読めない、腎機能低下で体力がなく疲れやすい、神経障害で歩行が困難、など)。
- 就労している場合は、仕事内容や職場での配慮、通勤方法なども具体的に記載します。
- 血糖コントロール状況だけでは認定されにくいことの理解: インスリン治療をしている、HbA1cが高いといったことだけでは、障害年金の認定には直結しません。あくまでも、それらの結果として生じた合併症による機能障害の程度が審査の対象となります。
障害年金申請の流れ(糖尿病の合併症の場合)
糖尿病の合併症による障害年金申請の一般的な流れは以下の通りです。
- 年金事務所・市区町村役場への相談: まずは制度の概要や必要書類を確認します。特に初診日の特定について相談しましょう。
- 初診日の確認・証明書類の準備: 糖尿病で最初に受診した医療機関から「受診状況等証明書」を取得するなどして初診日を証明します。
- 医師への診断書作成依頼: 障害認定日以降に、合併症に応じた診断書の作成を主治医に依頼します。
- 病歴・就労状況等申立書の作成: ご自身の状況を具体的に、かつ分かりやすく記載します。
- 年金請求書等の作成・提出: 必要書類を揃えて年金事務所または市区町村役場に提出します。
- 審査・結果通知: 通常3ヶ月~半年程度かかります。
社労士に障害年金申請を依頼するメリット
糖尿病の合併症による障害年金申請は、初診日の考え方や合併症の評価など、専門的な知識が求められる場面が多くあります。社会保険労務士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。
- 複雑な初診日(糖尿病自体の初診日)の特定と証明のサポート。
- 合併症の多様性に応じた適切な診断書様式の選択や、医師への依頼時のポイント伝達。
- 日常生活や就労への影響を的確に伝えるための「病歴・就労状況等申立書」作成支援。
- 複数の合併症がある場合の併合認定の可能性も考慮した申請戦略の提案。
- 煩雑な手続きの代行による、ご本人やご家族の精神的・時間的負担の軽減。
糖尿病の障害年金に関するよくある質問
Q1. 糖尿病と診断されただけでは障害年金はもらえませんか?
A1. 原則として、糖尿病と診断されただけでは障害年金の対象とはなりません。糖尿病による重篤な合併症を発症し、それによって日常生活や労働に著しい支障が生じている場合に、その合併症による障害として認定されます。
Q2. インスリン注射をしていれば障害年金をもらえますか?
A2. インスリン注射をしているという事実だけでは、障害年金の支給対象とはなりません。血糖コントロールの手段の一つであり、それ自体が障害の状態を示すものではないためです。重要なのは、インスリン治療をしてもなおコントロールが困難で、重篤な合併症が進行しているかどうかです。
Q3. 人工透析になったら必ず障害年金2級ですか?
A3. はい、糖尿病性腎症により人工透析療法を受けている場合は、原則として障害等級2級に認定されます(初診日や保険料納付要件を満たしている場合)。
Q4. 糖尿病性網膜症で視力がかなり落ちました。対象になりますか?
A4. はい、対象となる可能性があります。矯正視力や視野の程度が障害認定基準に定められた等級に該当すれば、障害年金を受給できます。眼科で精密な検査を受け、診断書を作成してもらう必要があります。
Q5. 足のしびれや痛み(神経障害)だけでも対象になりますか?
A5. 糖尿病性神経障害による手足のしびれや痛みが非常に強く、日常生活や労働に著しい支障をきたしている場合は、肢体の機能障害として評価され、対象となる可能性があります。麻痺の程度や歩行能力などが考慮されます。
Q6. 複数の合併症がある場合はどうなりますか?
A6. 例えば、糖尿病性網膜症と糖尿病性腎症(人工透析には至らないが腎機能低下)がある場合など、複数の合併症がそれぞれ一定以上の障害状態にあると認められれば、それらを総合的に評価する「併合認定」によって、より上位の等級に認定されることがあります。
ご相談は静岡障害年金サポートきぼうへ
糖尿病とその合併症は、長期にわたる治療と自己管理が必要であり、身体的・精神的、そして経済的にも大きな負担となり得ます。障害年金は、そのような状況下で療養生活を支えるための大切なセーフティネットです。
特に糖尿病の合併症による申請は、初診日の考え方や合併症の種類・程度の評価が複雑になることがあります。「自分は対象になるのだろうか」「手続きが難しそう」と感じたら、一人で悩まず、まずは障害年金専門の社会保険労務士にご相談ください。
当事務所では、糖尿病とその合併症に苦しむ方々の状況を丁寧に伺い、障害年金の受給に向けて最適なサポートを提供いたします。
この記事が、皆様の不安を少しでも和らげ、希望を持って次の一歩を踏み出すためのお手伝いとなれば幸いです。
プロフィール

- 社会保険労務士
-
ご覧いただきありがとうございます。
三島市・富士市・沼津市・熱海市・伊豆全域・御殿場中心に
静岡県全域の障害年金の請求サポートをしております。
障害年金について気になることやご質問があれば
お気軽にご相談ください。
一人でも多くの方が明るい未来へと歩み出せるよう、
全力でサポートいたします。
最新の投稿
- 7月 7, 2025コラム障害年金の遡及請求とは?過去分の受給可能性と申請ポイントを社労士が解説
- 7月 7, 2025コラム働きながら障害年金はもらえる?受給の可否を左右するポイントを社労士が解説
- 7月 7, 2025コラムがんで障害年金はもらえる?ステージ・治療中の申請ポイントを社労士が解説
- 7月 7, 2025コラム人工透析で障害年金はもらえる?等級2級の基準・申請時期を社労士が解説
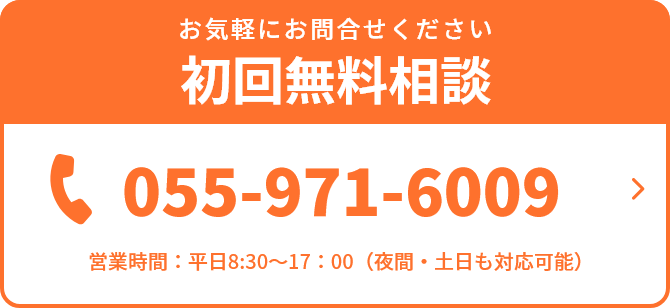
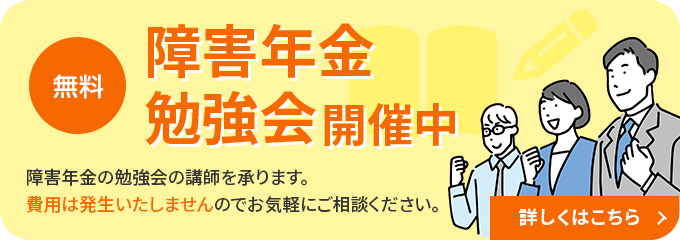

 初めての方へ
初めての方へ