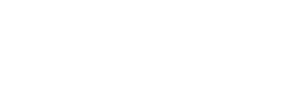がんで障害年金はもらえる?ステージ・治療中の申請ポイントを社労士が解説
目次
「がんと診断されたけれど、障害年金はもらえるのだろうか?」「治療の副作用で働くのがつらい」「今後の生活費が心配…」
がんと診断された方やそのご家族は、病気そのものへの不安に加え、治療による身体的・精神的な負担、そして経済的な問題に直面することが少なくありません。そのような状況において、治療と療養生活を支えるための一つの選択肢となるのが「障害年金」です。
がん(悪性新生物)は、その種類、進行度(ステージ)、治療法、そして何よりも現在の全身状態や日常生活への支障の程度によって、障害年金の支給対象となる可能性があります。
この記事では、障害年金申請代行を専門とする社会保険労務士が、がんで障害年金を受給するための条件、認定基準、申請のタイミングや注意点について、詳しく解説します。
この記事が、がんと闘病されている皆様とそのご家族にとって、障害年金制度への理解を深め、経済的な不安を少しでも和らげるための一助となれば幸いです。
がんと障害年金の基礎知識
まず、障害年金制度の概要と、がんがどのように障害年金の対象となるのかについてご説明します。
障害年金とは?
障害年金は、病気やケガによって法律で定められた障害の状態になった場合に支給される公的な年金です。初診日に加入していた年金制度に応じて、主に以下の2種類があります。
- 障害基礎年金: 初診日に国民年金に加入していた方(自営業者、専業主婦(夫)、学生、無職の方など)、または20歳前に初診日がある方が対象です。障害等級は1級と2級です。
- 障害厚生年金: 初診日に厚生年金に加入していた方(会社員や公務員など)が対象です。障害基礎年金に上乗せして支給され、障害等級は1級から3級まであります。3級よりも軽い障害状態の場合には障害手当金(一時金)が支給されることもあります。
がん(悪性新生物)も障害年金の対象です
がんは、障害年金の認定基準において「悪性新生物による障害」として明確に対象とされています。ただし、がんと診断されたという事実だけで自動的に支給されるわけではありません。
障害年金の審査では、主に以下の点が総合的に評価されます。
- 全身状態: 悪液質(体重減少、食欲不振、全身の衰弱)、倦怠感、貧血、発熱、疼痛(痛み)などの程度。日常生活の支障度を示す指標(PS: Performance Statusなど)も参考にされます。
- 局所の状態: がんが発生した部位(例:肺、胃、大腸、乳房、子宮など)による特有の症状や機能障害(例:肺がんによる呼吸困難、食道がんによる嚥下困難、大腸がんによる消化吸収障害や人工肛門の造設など)。
- 治療による影響: 手術後の後遺症、化学療法(抗がん剤治療)や放射線療法の副作用(吐き気、嘔吐、脱毛、倦怠感、しびれ、白血球減少など)が長期間持続し、日常生活や就労に著しい支障をきたしている場合。
- 転移・再発の有無: がんが他の臓器に転移したり、治療後に再発したりして症状が悪化し、全身状態が不良となった場合。
がんの進行度(ステージ)は障害状態を判断する上での参考情報の一つとはなりますが、ステージだけで等級が決定されるわけではありません。あくまでも、現在の「障害の状態」がどの程度であるかが最も重視されます。
がんで障害年金を受給するための条件
がんで障害年金を受給するためには、主に以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
- 初診日要件:がんの診断、またはがんの疑いで初めて医師の診療を受けた日が特定できること 「初診日」とは、がんの自覚症状や検診での異常所見などにより、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日を指します。確定診断がついた日ではなく、がんに関連する最初の受診日が初診日となります。
- 保険料納付要件:年金保険料を一定期間納付していること (がんの)初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間のうち、以下のいずれかを満たしている必要があります。
- 保険料納付済期間(免除・猶予・学生納付特例期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること。
- 初診日が令和8年3月31日以前にある場合は、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと(特例)。 (20歳前に初診日がある場合は、この納付要件は問われません)
- 障害状態要件:がんによる障害の程度が認定基準に該当すること 障害認定日(詳細は後述)において、がんによる障害の程度が、国が定める障害等級に該当している必要があります。「悪性新生物による障害」の認定基準では、全身の衰弱度、日常生活の困難さ、労働能力の喪失度合いなどが総合的に評価されます。
- 1級: 生命の維持に不可欠な身のまわり処理も不能で、常時介護を要するもの。PS(Performance Status)4相当。
- 2級: 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの。PS3相当。
- 3級 (障害厚生年金のみ): 労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。PS2相当。
- 上記はあくまで目安であり、個々の症状や状況によって総合的に判断されます。
がんの障害年金申請における重要なポイント
がんで障害年金を申請する際には、その特性を踏まえ、以下の点に特に注意して準備を進めることが重要です。
- 申請のタイミング(障害認定日)の検討:
- 原則: (がんの)初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日が障害認定日となります。
- 特例: 以下のような場合は、1年6ヶ月を待たずに障害認定日とされることがあります。
- 人工肛門または新膀胱を造設した場合:造設した日から起算して6ヶ月を経過した日。
- 喉頭全摘出の場合:全摘出した日。
- 在宅酸素療法を施行中の場合:在宅酸素療法を開始した日(ただし、常時施行している場合)。
- その他、治療効果が期待できないと医学的に判断され、症状が安定し、これ以上改善が見込めない状態(症状固定に類する状態)と認められる場合。 治療中であっても、日常生活や就労に著しい支障が生じている場合は、障害認定日の到来を待たずに申請(障害認定日請求)を検討できるか、あるいは事後重症請求という形で申請できる可能性があります。主治医や専門家とよく相談しましょう。
- 診断書の内容の正確性と具体性: 診断書は「血液・造血器・その他の障害用」(様式第120号の6-(1))を使用することが多いですが、がんの部位によっては「呼吸器疾患の障害用」(様式第120号の3)、「消化器疾患の障害用」(様式第120号の6-(3))など、他の様式を用いる場合もあります。主治医と相談し、最も適切な様式を選びましょう。 医師には以下の情報を正確かつ具体的に記載してもらう必要があります。
- がんの病名、組織型、確定診断日、進行度(ステージ)。
- 転移の有無、転移部位。
- これまでの治療経過(手術、化学療法、放射線療法の種類、期間、効果、副作用の詳細)。
- 現在の自覚症状(疼痛の部位・程度・頻度、倦怠感の程度、食欲不振、体重減少、呼吸困難、吐き気、しびれなど)。
- 他覚所見、主要な検査成績(血液検査の異常値、画像検査の所見など)。
- 全身状態の評価(Performance Status(PS)は特に重要です)。
- 日常生活動作(ADL)の状況(食事、入浴、更衣、排泄、移動など)や、活動能力の制限度合い。 ご自身の辛い症状や日常生活での具体的な支障、治療の副作用の苦しさなどを、遠慮せずに医師に伝え、診断書にしっかりと反映してもらうことが極めて重要です。
- 病歴・就労状況等申立書の丁寧な作成: この書類は、がんの発見のきっかけから診断、治療の経過(入院・通院状況、副作用の具体的な内容と期間)、現在の自覚症状、そしてそれによって日常生活や就労にどのような支障が出ているかを、ご自身の言葉で時系列に沿って詳細に記載するものです。
- 痛みがどの程度生活に影響しているか(例:夜も眠れない、特定の動作ができないなど)。
- 倦怠感がどのくらい強く、どれくらい持続するか(例:午前中しか活動できない、少し動くとすぐに横になりたくなるなど)。
- 食事の状況(例:食欲がなくほとんど食べられない、吐き気で食事が苦痛など)。
- 家族のサポート状況や、精神的な苦痛、将来への不安なども、可能な範囲で記載することができます。
- 就労していた場合は、治療のために休職・退職に至った経緯や、仕事と治療の両立の困難さなども具体的に記述しましょう。
- 就労状況との関連: 働いているからといって、必ずしも障害年金がもらえないわけではありません。がん治療の影響で、以前と同じように働けなくなったり、勤務時間を短縮したり、職場から特別な配慮を受けたりしている場合は、その状況を具体的に伝えることが重要です。
障害年金申請の流れ(がんの場合)
がんによる障害年金申請の一般的な流れは以下の通りです。障害認定日の判断や治療経過の詳細な記述がポイントとなります。
- 年金事務所・市区町村役場への相談: まずは制度の概要や必要書類を確認します。特に初診日の特定や障害認定日の考え方について相談しましょう。
- 初診日の確認・証明書類の準備: がんで最初に受診した医療機関から「受診状況等証明書」を取得するなどして初診日を証明します。
- 医師への診断書作成依頼: 障害認定日以降に、主治医に診断書の作成を依頼します。
- 病歴・就労状況等申立書の作成: ご自身の状況を具体的に、かつ分かりやすく記載します。
- 年金請求書等の作成・提出: 必要書類を揃えて年金事務所または市区町村役場に提出します。
- 審査・結果通知: 通常3ヶ月~半年程度かかります。
社労士に障害年金申請を依頼するメリット
がんの障害年金申請は、病状の進行や治療状況によって状態が変化しやすく、また、その多様性から申請書類の作成にも専門的な知識が求められます。社会保険労務士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。
- がんの種類や進行度、治療状況に応じた適切なアドバイスと申請戦略の立案。
- 複雑な障害認定日の判断や、特例適用の可能性についての検討。
- 診断書作成依頼時のポイント(特にPSやADL、副作用の記載など)や、記載内容のチェック。
- 全身状態や日常生活への影響、治療の副作用の辛さを的確に伝えるための「病歴・就労状況等申立書」作成支援。
- 煩雑な手続きの代行による、ご本人やご家族の精神的・時間的負担の軽減。
がんの障害年金に関するよくある質問
Q1. がんと診断されたら、すぐに障害年金を申請できますか?
A1. 原則として、がんの初診日から1年6ヶ月経過した日が障害認定日となるため、すぐには申請できません。ただし、人工肛門の造設や喉頭全摘出など特定の状態になった場合や、症状が急速に悪化し治療効果が期待できない状態と判断された場合は、1年6ヶ月を待たずに申請できることがあります。
Q2. がんのステージが低いと障害年金はもらえませんか?
A2. ステージだけで判断されるわけではありません。ステージが低くても、治療の副作用が重篤で長期間日常生活に支障が出ている場合や、手術の後遺症が大きい場合などは、障害年金の対象となる可能性があります。重要なのは現在の「障害の状態」です。
Q3. 抗がん剤治療の副作用で辛いのですが、これも障害として認められますか?
A3. はい、認められる可能性があります。抗がん剤治療による重篤な副作用(強い倦怠感、吐き気、しびれ、白血球減少による易感染性など)が長期間継続し、日常生活や就労に著しい支障をきたしている場合は、その副作用による影響も障害の程度として評価されます。
Q4. 働いていても障害年金はもらえますか?
A4. 働いているという理由だけで不支給になるわけではありません。がん治療の影響で、仕事内容に大きな制約があったり、時短勤務や休職を余儀なくされたり、職場からの特別な配慮が必要であったりする場合には、受給できる可能性があります。
Q5. 末期がんと診断されました。障害年金はどうなりますか?
A5. 末期がんと診断され、余命宣告を受けた場合でも、障害年金の審査はあくまで現在の障害の状態(全身の衰弱度、日常生活の困難さなど)に基づいて行われます。症状が重篤であれば、1級や2級に該当する可能性が高まります。速やかに申請手続きを進めることをお勧めします。
Q6. 再発・転移した場合、再度申請できますか?または等級が変わりますか?
A6. すでに障害年金を受給している方が、がんの再発や転移によって症状が悪化した場合は、より上位の等級への変更を求める「額改定請求」を行うことができます。まだ受給していない方が再発・転移し、障害の状態が悪化した場合は、その時点の状態に基づいて新たに申請することができます。
ご相談は静岡障害年金サポートきぼうへ
がんは、誰にとっても大きな試練です。治療に専念し、少しでも穏やかな療養生活を送るためには、経済的な安定が不可欠です。障害年金は、そのような状況にある方々を支えるための大切な制度です。
がんの進行状況や治療法、副作用の出方は人それぞれであり、申請のタイミングや書類の書き方もケースバイケースです。「自分の場合はどうなんだろう」「申請手続きが難しそう」と感じたら、一人で抱え込まず、まずは障害年金専門の社会保険労務士にご相談ください。
当事務所では、がんと闘病されている方とそのご家族の状況を丁寧に伺い、障害年金の受給に向けて最適なサポートを提供いたします。
この記事が、皆様の不安を少しでも和らげ、希望を持って前へ進むための一助となれば心より幸いです。
プロフィール

- 社会保険労務士
-
ご覧いただきありがとうございます。
三島市・富士市・沼津市・熱海市・伊豆全域・御殿場中心に
静岡県全域の障害年金の請求サポートをしております。
障害年金について気になることやご質問があれば
お気軽にご相談ください。
一人でも多くの方が明るい未来へと歩み出せるよう、
全力でサポートいたします。
最新の投稿
- 7月 7, 2025コラム障害年金の遡及請求とは?過去分の受給可能性と申請ポイントを社労士が解説
- 7月 7, 2025コラム働きながら障害年金はもらえる?受給の可否を左右するポイントを社労士が解説
- 7月 7, 2025コラムがんで障害年金はもらえる?ステージ・治療中の申請ポイントを社労士が解説
- 7月 7, 2025コラム人工透析で障害年金はもらえる?等級2級の基準・申請時期を社労士が解説
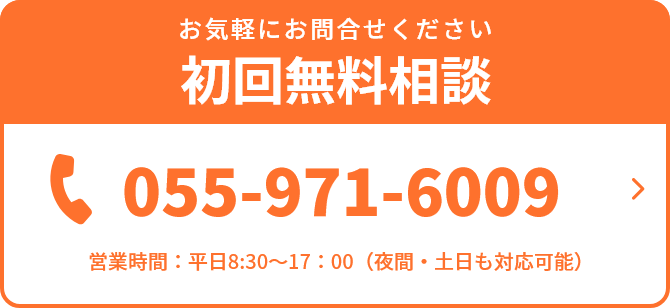
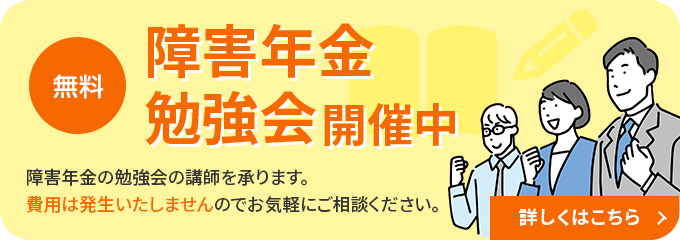

 初めての方へ
初めての方へ