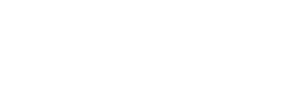働きながら障害年金はもらえる?受給の可否を左右するポイントを社労士が解説
目次
病気やケガを抱えながらも、生活のため、あるいは社会とのつながりのために働き続けたいと考える方は少なくありません。しかし、「働いていると障害年金はもらえないのではないか…」という不安から、申請をためらってしまうケースも耳にします。
確かに、障害年金の審査において就労状況は重要な判断材料の一つです。しかし、「働いている=障害年金はもらえない」と一概に決まるわけではありません。 どのような仕事内容で、どの程度の時間働き、職場でどのような配慮を受けているかなど、その「働き方」や「働ける状態」が総合的に評価され、受給の可否が判断されます。
この記事では、障害年金申請代行を専門とする社会保険労務士が、働きながら障害年金を受給するための条件、就労状況が審査にどのように影響するのか、そして申請時の注意点について詳しく解説します。
この記事が、病気やケガと向き合いながら働く皆様にとって、障害年金制度への正しい理解を深め、経済的な支援を得るための一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。
「働きながら障害年金」の基本的な考え方
まず、障害年金制度と就労の関係について基本的な考え方を押さえておきましょう。
障害年金制度の目的
障害年金は、病気やケガによって日常生活や仕事に支障が出ている方々の生活を支えるための公的な所得保障制度です。単に収入が減ったことに対する補填だけでなく、障害によって生じる様々な生活上の困難さに対する支援という意味合いも含まれています。
「働いている=障害が軽い」とは限らない
障害年金の審査では、「労働能力の程度」が重要な判断要素となります。しかし、単に「就労している」という事実だけで、直ちに「労働能力に問題なし=障害が軽い」と判断されるわけではありません。 例えば、
- 職場の特別な配慮や同僚の多大なサポートがあって、ようやく仕事を続けられている。
- 以前と同じ仕事はできず、大幅に業務内容が軽減されたり、短時間勤務になったりしている。
- 無理をして働いているが、実際には体調が悪く、いつまで続けられるか不安な状態である。
といったケースでは、就労していても障害の程度が重いと判断される可能性があります。
障害の種類による評価の違い
障害の種類(精神疾患、内部障害、肢体障害など)によって、就労状況が審査に与える影響の度合いや評価の視点が異なる場合があります。
働きながら障害年金を受給するための条件と審査のポイント
働きながら障害年金を受給するためには、通常の障害年金申請と同様に以下の3つの基本条件を満たす必要があります。
- 初診日要件: 障害の原因となった病気やケガで初めて医師または歯科医師の診療を受けた日が特定できること。
- 保険料納付要件: 初診日の前日において、一定期間の年金保険料を納めていること。
- 障害状態要件: 障害の程度が、国が定める障害等級(1級・2級・3級)に該当すること。
このうち、「働きながら」の場合に特に重要となるのが「3. 障害状態要件」における労働能力の評価です。
労働能力の評価で重視されるポイント
審査では、以下の点が総合的に考慮されます。
- 仕事内容:
- 以前と同じ業務内容か、より負担の軽い業務に変更されたか。
- 単純作業か、複雑な判断を伴う業務か。
- 責任の度合いはどの程度か。
- 勤務時間・日数:
- フルタイム勤務か、パートタイム(短時間)勤務か。
- 週の勤務日数はどのくらいか。
- 収入額:
- 収入額は一つの目安とされますが、収入が高いからといって必ずしも不支給になるわけではありません。仕事内容や他の要素と総合的に判断されます。
- 職場での配慮・援助の状況:
- 通院のための休暇取得、休憩時間の確保、業務量の調整、通勤時の配慮など、会社から特別な配慮を受けているか。
- 上司や同僚から日常的なサポートを受けているか。
- 障害者雇用枠での就労か、一般雇用か。
- 就労の安定性・継続性:
- 現在の仕事をどのくらいの期間継続できているか。
- 頻繁に休職したり、体調不良で欠勤が多かったりしないか。
- 過去に転職を繰り返していないか(特に体調が原因で)。
障害の種類別・就労状況の評価傾向
- 精神疾患(うつ病、双極性障害、統合失調症、発達障害など)の場合: 精神疾患の場合、就労していると「日常生活能力や労働能力が一定程度保たれている」と見なされやすく、特に2級の認定においては慎重な判断がなされる傾向があります。しかし、上記のような職場の特別な配慮や援助、極めて単純な作業、ごく短時間の労働、不安定な就労状況などの場合は、受給の可能性が出てきます。診断書や病歴・就労状況等申立書で、いかに就労が困難であるか、どのようなサポートがあって成り立っているかを具体的に示すことが重要です。
- 内部障害(がん、心疾患、腎疾患(人工透析など)、糖尿病、呼吸器疾患など)の場合: 検査数値や自覚症状、治療状況に加え、日常生活や仕事への支障度が総合的に評価されます。例えば、人工透析を受けている方は原則2級とされますし、ペースメーカーや人工関節を装着した方は原則3級(障害厚生年金の場合)とされるなど、治療内容によっては就労していても一定の等級に認定されやすいケースがあります。治療と仕事の両立の困難さを具体的に伝えることが大切です。
- 肢体障害(手足の麻痺、欠損、関節疾患など)の場合: 麻痺の範囲や程度、関節の可動域、筋力、日常生活動作(ADL)への支障が比較的客観的に評価されやすい障害です。就労している場合でも、その仕事が障害のない部分の機能を活用したものであったり、職場環境がバリアフリー化されていたり、業務内容に特別な配慮がなされていたりする状況であれば、受給の可能性があります。
障害等級と就労の関係(目安)
- 障害等級3級(障害厚生年金のみ対象): 「労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とされています。つまり、何らかの形で働きながらも、その労働には大きな制約がある状態が想定されています。一般的に、働きながら受給しやすいのはこの3級と言えます。
- 障害等級2級: 「労働により収入を得ることができない程度のもの」とされており、原則として就労は困難な状態とされます。しかし、例外的に、職場の多大な配慮や援助のもとで、ごく軽微な作業や短時間の就労に従事している場合などは、2級に認定されることもあります。
- 障害等級1級: 「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの」とされ、労働は基本的に不可能な状態です。
働きながら障害年金を申請する際の注意点
- 診断書の記載内容: 医師に、ご自身の就労状況(仕事内容、勤務時間、職場での配慮など)や、仕事をする上での困難さを正確に伝え、診断書に具体的に記載してもらうことが非常に重要です。「一般状態区分表」や「日常生活能力の判定」といった項目も、就労状況を考慮して実態に即した評価をしてもらいましょう。
- 病歴・就労状況等申立書の記述: この書類は、ご自身の言葉で障害の状態や就労状況を伝える唯一の機会です。仕事内容、勤務状況、職場から受けている配慮、仕事上の具体的な困難さ、なぜその状態で働けているのか(あるいは、なぜ働かざるを得ないのか、無理をしているのか)などを、包み隠さず具体的に、かつ丁寧に記述しましょう。
- 安易な自己判断は禁物: 「フルタイムで働いているから無理だろう」「これくらいの収入があるから対象外だ」とご自身で判断して申請を諦めてしまうのは非常にもったいないことです。専門家である社会保険労務士に相談し、受給の可能性を検討することをお勧めします。
障害年金を受給しながら働く場合の留意点
- 更新時の審査(障害状態確認届): 障害年金には有効期限があり、定期的に「障害状態確認届(更新時の診断書)」を提出し、障害状態の再審査を受ける必要があります。その時点での就労状況や症状の変化によって、等級が変更されたり、支給が停止されたりする可能性があります。
- 症状が悪化した場合: 障害年金の受給中に症状が悪化した場合は、より上位の等級への変更を求める「額改定請求」を行うことができます。
- 就労状況が大きく変化した場合: 就労状況が大きく変わった場合(例:一般雇用から障害者雇用へ、フルタイムから短時間へ、あるいはその逆など)は、更新時の審査に影響を与える可能性があります。
社労士に依頼するメリット
「働きながら」の障害年金申請は、就労の実態をいかに正確かつ効果的に伝えるかが鍵となります。社会保険労務士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。
- 個別の就労状況を詳細にヒアリングし、受給可能性を的確に判断します。
- 「働いている」という事実が不利にならないよう、診断書依頼時のアドバイスや「病歴・就労状況等申立書」の作成をサポートし、就労の実態や困難さを具体的にアピールします。
- 各障害種別(精神疾患、内部障害、肢体障害など)に応じた、就労状況の評価ポイントを踏まえた申請戦略を立案します。
- 煩雑な書類準備や年金事務所とのやり取りを代行し、ご本人の負担を軽減します。
「働きながら障害年金」に関するよくある質問
Q1. 正社員としてフルタイムで働いていたら、障害年金は絶対にもらえませんか?
A1. 絶対にもらえないわけではありません。正社員・フルタイムであっても、仕事内容が大幅に軽減されていたり、常に上司や同僚のサポートが必要不可欠であったり、通勤や業務遂行に多大な困難が伴うなど、その実態によっては受給できる可能性があります。特に障害厚生年金の3級であれば、可能性は十分あります。
Q2. 収入がいくらまでなら障害年金をもらえますか?
A2. 障害年金の審査において、収入額だけで受給の可否が一律に決まる明確な基準はありません。収入はあくまで判断材料の一つであり、仕事内容、勤務時間、職場での配慮などと総合的に評価されます。ただし、一般的に健常者と同程度の収入を得ている場合は、労働能力に大きな支障がないと見なされやすくなる傾向はあります。 (※20歳前傷病による障害基礎年金の場合は、本人の所得による支給制限があります。)
Q3. 精神疾患(うつ病、双極性障害、発達障害など)で働きながら受給するのは難しいですか?
A3. 精神疾患の場合、他の障害に比べて就労状況が等級判断に影響しやすい傾向はありますが、不可能ではありません。職場での配慮の程度、業務内容の単純さ、勤務時間の短さ、コミュニケーションの必要度合いなどがポイントになります。「一般雇用でフルタイム、特に配慮なし」という状況では難しいことが多いですが、実態を丁寧に伝えることで道が開けることもあります。
Q4. 障害者雇用枠で働いていますが、有利になりますか?
A4. 障害者雇用枠で働いているという事実は、何らかの障害があり、就労に際して配慮が必要であることの一つの証左とはなります。しかし、それだけで必ず有利になるわけではなく、実際の仕事内容や勤務状況、受けている配慮の具体的な内容などが総合的に評価されます。
Q5. 障害年金をもらいながら働くと、年金額が減らされたりしますか?
A5. 20歳前傷病による障害基礎年金を除き、障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)には、就労による収入によって年金額が減額されたり支給停止されたりする仕組みは原則としてありません。老齢年金との調整で一部支給停止になる場合はあります。
Q6. 障害年金を受給していることを会社に知られることはありますか?
A6. 日本年金機構から会社へ障害年金の受給状況が通知されることはありません。ご自身から伝えなければ、原則として会社に知られることはありません。
ご相談は静岡障害年金サポートきぼうへ
病気やケガを抱えながら働くことは、決して簡単なことではありません。経済的な不安を抱えながら無理をして働き続けることは、症状の悪化にもつながりかねません。
「働いているから障害年金は無理」と最初から諦めてしまうのではなく、まずはご自身の状況で受給の可能性があるのかどうかを専門家に相談してみることが大切です。障害年金は、治療と仕事の両立を目指す方々にとって、心強い経済的な支えとなり得る制度です。
当事務所では、働きながら障害年金の申請をお考えの方々の状況を丁寧に伺い、個別のケースに合わせた最適な申請戦略をご提案し、受給に向けて全力でサポートいたします。
この記事が、皆様の不安を少しでも解消し、希望を持って毎日を過ごすための一助となれば幸いです。
プロフィール

- 社会保険労務士
-
ご覧いただきありがとうございます。
三島市・富士市・沼津市・熱海市・伊豆全域・御殿場中心に
静岡県全域の障害年金の請求サポートをしております。
障害年金について気になることやご質問があれば
お気軽にご相談ください。
一人でも多くの方が明るい未来へと歩み出せるよう、
全力でサポートいたします。
最新の投稿
- 7月 7, 2025コラム障害年金の遡及請求とは?過去分の受給可能性と申請ポイントを社労士が解説
- 7月 7, 2025コラム働きながら障害年金はもらえる?受給の可否を左右するポイントを社労士が解説
- 7月 7, 2025コラムがんで障害年金はもらえる?ステージ・治療中の申請ポイントを社労士が解説
- 7月 7, 2025コラム人工透析で障害年金はもらえる?等級2級の基準・申請時期を社労士が解説
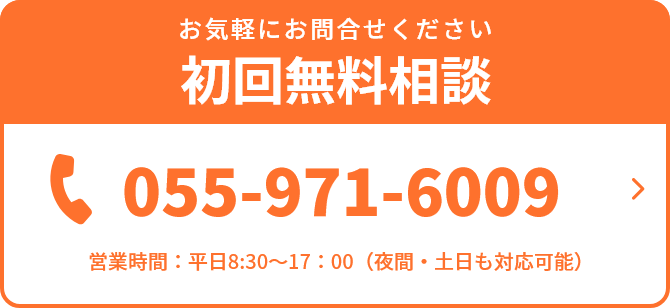
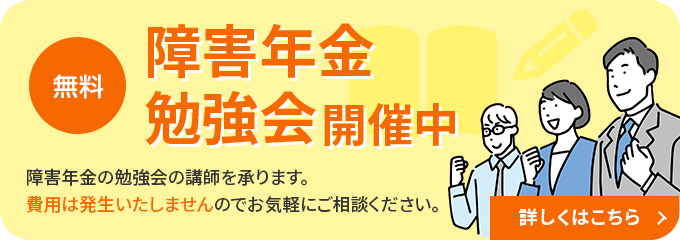

 初めての方へ
初めての方へ